はじめまして。ご覧いただきありがとうございます。
Mちゃんと申します。
Xでも情報発信をしているので、そちらも見てみてください!
https://x.com/BPshuki
私は現在20代後半の会社員で、2020年に大学を卒業して社会人になりました。
ごく普通の家庭に育ち、親からの経済的援助も特にない中で、コツコツと資産を積み上げてきました。
いや、一般的に言うと貧乏なのかもしれません。
大学在学中は一人暮らしでしたが仕送りなんて一切ありませんでしたし、(学費は払ってくれてた)
奨学金は日本学生支援機構の奨学金を無利子で(第一種奨学金で)借りていました。
第一種奨学金が借りられるということは親の年収が高くないということです。
わたしの大学は1から2年目は神奈川は港北区、3~4年で東京は港区に通学するのですが、港区で暮らせるはずもなく4年間港北区のアパートで家賃と格闘していました。
けっこう貧乏な学生だったと思います。
大学時代は経済学部に在籍していましたが、それよりも大きかったのは大学で貧乏を経験したことでした。
大学近くのマンションを買ってもらえた同期や有名企業のご子息、あるいは芸能人など
自分が故郷で会ったようなことがない人種に触れたことが、今思えば人生のターニングポイントだったかもしれません。
社会人になってすぐに穂高唯希さんとFIREという考え方に感銘を受け給与の大部分を貯蓄や投資に回す生活を続け、結果的に20代のうちに資産5,000万円を達成することができました。
「特別な才能があったわけじゃない」
「副業で大成功したわけでもない」
むしろ、本業に集中しながら支出を抑えて、早めに投資を始めたことがすべての出発点です。
現在の職業は一般的な会社員で、外資系企業で働いています。年収は変動がありますが、ここ数年は900万円〜1,000万円の間を推移しています。
この辺は別途、有料noteで詳しくお話させていただきます。
自分は「特別」ではありません
正直に言うと、私自身、投資を始めたばかりの頃は不安でいっぱいでした。
2022年の暴落も経験しましたし、追証も経験して「投資って意味あるのかな…」と何度も思いました。
それでも、情報を集めて学び、自分なりにリスクと向き合いながら行動してきたことで、ようやくここまで来ることができました。
この記事では、そんな私の資産形成のリアルな道のりを、できるだけ具体的に、そして隠しごとなしで書いていきます。
もし今、「自分には無理かも」と思っている方がいたら、きっと参考になるはずです。むしろ、そう思っている人にこそ読んでもらいたいです。
なお、このnoteでは私の実際の給料明細や資産推移の詳細も可能な限り公開しています。(有料部分で)
SNS、とくにX(旧Twitter)では「若くして資産5,000万!」などと謳っている投稿をよく見かけますが、正直、証拠のない主張には注意した方がいいと思っています。
なぜなら、ああいった数字はいくらでも加工できるからです。資産額の画像も、グラフも、ちょっと編集すればそれっぽく見えてしまう。
私自身、そんな空虚な「数字だけのマウント合戦」にちょっとモヤモヤしていたので、このブログでは誠実に、実物ベースでの数字が見えるという価値を提供したいと思いました。
資産形成のきっかけとマインドセット
「なんでそんなにお金を貯められたの?」
「どうしてそこまで資産形成に本気になれたの?」
よく聞かれる質問です。
でも実は、私も最初から「お金を貯めるぞ!」と燃えていたわけではありません。
むしろ、大学を卒業したばかりの頃は、給料日が楽しみで、服やガジェット、飲み会などに気軽にお金を使っていました。
ただ、その頃にふと気づいたことがありました。
「このまま働き続けるのって、果たして自由なんだろうか?」と。
「自由に生きたい」がスタートだった
私は昔からわりと一人で考えごとをするのが好きで、「理想の生き方ってなんだろう?」と考える時間が多かった方です。
社会人になって間もないころ、たまたまネットで「FIRE(Financial Independence, Retire Early)」という言葉を目にしました。
「経済的に自立し、早期に会社を辞めて自由に生きる」という考え方に、心の底から衝撃を受けました。
そのときに読んだのが、FIREを実践された穂高唯希さんのブログや書籍でした。
彼は会社員としての生活を淡々と送りながらも、徹底的に支出を管理し、株式投資を通じて若くしてFIREを実現されています。
「こんな生き方があるのか……」と感動すると同時に、彼の生き方に憧れを抱いたのを今でも覚えています。
その頃から、「投資で一発逆転」ではなく、「収入をきちんと貯めて、投資を習慣にする」という地道なスタイルに惹かれていきました。
お金を貯めることが「目的」じゃなくて「手段」になった
多くの人は「お金持ちになりたい」と口にします。でも実際にそのお金を何に使いたいのかを真剣に考えている人は、意外と少ない気がします。
私の場合は明確でした。
- 将来、働くことを「選べる」ようになりたい
- 嫌なことを我慢しないで済むようになりたい
- 大切な人との時間を、もっと自由に使いたい
だからこそ、「お金は目的じゃなくて、自由を手に入れるための手段だ」と心から思えたとき、毎日の行動が大きく変わりました。
投資への考え方も大きく変わった
初めてNISA口座を開設したとき、正直言って「ちょっと怖いな」と思いました。元本割れするかも、とか、暴落が来たら終わりだ、というような感情が先に来ていました。
でも、勉強すればするほど、こう思うようになりました。
「何もしないことの方が、むしろリスクでは?」
日本円だけで貯金していても、インフレで価値が目減りしていく。長期的に見れば、投資はリスクを管理しながらお金の価値を保ち、増やす手段なのだと学びました。
投資を始めたことで、「お金に働いてもらう」という感覚が自然と身につき、「資産を増やすこと=生活の安定と選択肢を増やすこと」だと実感しています。
自分の「欲」を明確にした
資産形成の過程で気づいたことがあります。それは、「自分の本当の欲を知ることが大事」ということ。
- 高級車はいらないけど、平日の昼にカフェでゆっくりしたい
- 高い服よりも、清潔感と機能性が大事
- 豪華な旅行よりも、ストレスなく生きたい
そういった「自分の欲望の解像度」が高くなると、無駄な出費が自然と減っていきます。
お金を使わないことが目的ではなく、本当に大切なことにお金を使うことが目的になったからです。
「資産形成=人生の再設計」だと気づいた
私にとって資産形成は、ただの数字のゲームではありませんでした。
「どう生きたいか?」を問う、自分自身との対話の時間でもあったんです。
なんにも考えていなかった過去の自分に言いたいです。
「正確な情報と大胆な判断が、人生を変えるよ」
もし今、毎月1万円しか貯金できなくても、何かを変えたいという気持ちがあるなら、それは十分すぎるスタートです。
次章では、私が実際にどんなペースで資産を増やしていったのか、年次ごとの資産推移とともにご紹介していきます。
年ごとの資産推移グラフと内訳
noteでは、私が2020年に大学を卒業してから現在に至るまで、どのようなペースで資産を増やしてきたのかを具体的に公開します。
年収、投資、支出、相場の影響など、資産形成にはさまざまな要素が絡んできますが、noteではなるべくリアルに数字をお見せしようと思います。
■ 資産の増え方は「後半加速型」
見てわかる通り、2023年あたりから資産残高が一気に増え始めています。これは「収入の増加」だけでなく、「複利効果+株式相場の上昇+円安による外貨資産の膨張」の影響が重なった結果です。
特に2023〜2024年は、米国ETFや日本株インデックスの評価額が上がったことが大きな要因でした。私のようなインデックス投資メインのスタイルでも、相場の波に素直に乗れたことで、想像以上の加速がありました。
■ 毎月の貯蓄・投資の内訳(2025年現在)
- 給与手取り:約65万円前後
- 固定支出:家賃10万円、生活費10万円、保険なし
- 月間投資額:20〜25万円(新NISA、iDeCo、特定口座)
- 残りは生活防衛資金や旅行などのために現金確保
「我慢して節約」というよりも、お金を使う対象を厳選した結果、自然と貯まっていったという感覚に近いです。飲み会を毎週行っていた頃に比べると、「使わないのに満たされてる」という不思議な気持ちもあります。
■ 一番大きな学び:「時間の力は偉大」
資産形成をしていく中で、何より強く実感したのは「時間は裏切らない」ということです。
- 早く始めるほど複利効果が効く
- 相場の浮き沈みにも動じなくなる
- 手取りが増えると積立額も増やせる
つまり「時間を味方にする」ことが、5,000万円に最も近道だったと感じています。焦って大きく稼ごうとせず、地道に積み上げたことが、結果的に大きな成果につながりました。
収入編:どう稼いだか?
資産5,000万円と聞くと、「副業で月100万稼いだんじゃない?」「投資でテンバガー引いたのでは?」と想像する方もいるかもしれません。
でも実際のところ、私は本業一本で、地道に給与を伸ばしてきたタイプです。
確かに、爆発的な収入源があったわけではありません。
ただ、自分の得意な領域で評価される場所に身を置くこと、昇給につながる選択を意識すること、これをコツコツ重ねた結果、年収もじわじわ上がっていきました。
■ 新卒時代~20代中盤:昇給のタネを撒いた時期
私が新卒で入社したのは、そこまで高給ではない業界の企業でした。年収でいうと、初任給は月23万円程度、年収ベースで400万円台。
そこからスキルを磨いて、転職を前提にキャリアを積み上げていく戦略をとりました。
といっても、転職エージェントを使って動いたのは社会人3年目。
その頃にはTOEICのスコアを上げたり、データ分析系の知識を身につけたり、「いつでも市場に出せる自分」を意識して動いていました。
■ 社会人4年目:転職で一気に収入アップ
社会人4年目で外資系企業へ転職。これが収入面ではかなり大きな転機でした。
年収は一気に約750万円まで伸びました。英語のスキル、論理的思考、ドキュメント作成力などが評価され、オファーも複数いただけたのが自信になりました。
外資系は成果が可視化されやすく、成果主義なので、「自分が出した価値」=「年収」に直結しやすいと感じました。
その分プレッシャーも大きいですが、「時間に縛られずに稼げる」という意味では、資産形成に向いていたと思います。
■ 本業に集中して副業はほぼなし
よく聞かれるのが「副業してましたか?」という質問ですが、答えは**「していません」。
実は、資産がある程度増えてからブログや投資系SNSを始めましたが、金額的には微々たるもので、主な収入源はあくまで給与所得**です。
理由としては、
- 本業のパフォーマンスを上げた方が年収アップに直結する
- 労働時間ではなく、昇給や昇格で時給単価を上げることに集中したかった
- 副業にエネルギーを割くと、長期戦で疲れる
このように考えていたからです。
**「副業で10万円稼ぐ努力」より、「本業で昇給して月10万円増やす仕組み作り」**を意識していました。
■ 収入の使い方:上がった分は貯める・投資する
収入が上がると、つい生活レベルを上げたくなりますよね。でも私は、**「生活レベルはあえて据え置きにする」**ことを徹底しました。
昇給しても家賃は上げない。服や食費も変わらない。
その代わり、余剰分を即、証券口座に移して投資へ回すというルーティンを作っていました。
この仕組みが、資産形成を加速させてくれました。
つまり、稼いだ額より「残した額」がすべてだと気づいたんです。
■ 「特別な才能」より「仕組みと習慣」
ここまで読んでくださった方なら分かると思いますが、私は何かに突出して優れているわけではありません。
でも、資産形成においては「仕組みと習慣の力」が何より大きかったです。
- 本業を最大化する
- 生活レベルを上げずに固定する
- 増えた収入は即投資に回す
この3つを習慣化したことが、収入アップ→資産拡大の王道ルートでした。
6. 投資編:どう増やしたか?
資産を「貯める」だけでは5,000万円という金額に20代で到達するのは正直厳しいです。
私の場合、資産が加速的に増えていった最大の要因はやはり**「投資」**です。
ただ、最初からうまくいったわけではありません。
むしろ投資を始めたばかりの頃は、怖さもありましたし、少し失敗も経験しました。
この章では、私がどんな投資スタイルをとっているか、どんな商品を買っているか、そして何に気をつけているかを詳しくお話しします。
■ 投資スタートは社会人1年目、月1万円から
投資を始めたのは、社会人になってすぐ。2020年、NISAについて調べているうちに「つみたてNISA」が始まったことを知り、「これなら失敗してもリスクは少なそうだな」と思って始めたのがきっかけでした。
最初は月1万円だけ。
当時はまだ投資に対して半信半疑で、「最悪なくなってもいいお金」としてスタートしました。
■ 投資スタイル:インデックス投資をベースに
基本的にはインデックス投資メインです。理由はシンプルで、個別株のように日々の値動きに一喜一憂したくなかったから。
買っている主な銘柄は以下の通り:
● 米国ETF(特定口座/NISA枠)
- VOO(S&P500)
- VTI(全米株式)
- VT(全世界株式)
- QQQ(ナスダック100)※少額
● 日本株ETF(東証)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- SBI・Vシリーズ(全米株式など)
● 個別株(少額保有)
- Apple、Microsoft、NVIDIA(米国)
- 任天堂、オリエンタルランド(日本)
● 仮想通貨(投資総額の10%以内)
- Bitcoin(BTC)
- Ethereum(ETH)
■ 投資の「仕組み化」がカギ
重要なのは、投資を生活の中に組み込んだことです。
- 毎月の給料日に積立設定を自動で引き落とし
- ボーナス月は追加投資
- 証券口座には基本ログインしない(見ると不安になるので)
つまり、「考えなくても資産が増えていく状態」を作ったのです。
行動に意思を介在させないことが、継続の最大のコツでした。
■ 怖さを感じたのはコロナショックとウクライナ危機
投資を始めてから、何度か「本当にこのままでいいのか?」と不安になる局面がありました。
- 2020年のコロナショック
- 2022年のウクライナ侵攻と米国株下落
- 金利上昇による株価の停滞
それでも積立は止めませんでした。
むしろ「下がったら買い場」という視点に切り替えたことで、下落時にも淡々と買い続けることができました。
■ 投資で大事にしているマインドセット
- 他人と比較しない
→ SNSを見て焦ると、だいたい失敗します。マイペースが一番。 - タイミングを計らない
→ 下がるときは買えないし、上がるときは買いにくい。なら毎月同じ日に買うのが一番楽。 - 「今」使わないお金は投資する
→ 現金を握りすぎていると、むしろ不安になる。 - 暴落も味方にする
→ 「株が下がった=チャンス」と思えるようになると、人生がラクになります。
■ 「投資=ギャンブル」の思い込みを超えるまで
私も最初は、「投資=怖い」「損するかも」としか思えませんでした。
でも、FIRE達成者や実際に資産を築いている人たちの考え方に触れる中で、**「投資は、長期で続けると確率的に勝てるゲーム」**だということが分かってきました。
ギャンブルと違うのは、時間が味方をしてくれるという点。
だからこそ、20代のうちに始めたことが、最大の勝因だったと思っています。
■ まとめ:投資で資産は「雪だるま式」に増える
貯金だけでは、増えません。
でも、貯めたお金を適切なリスクの中で運用することで、資産は加速的に増えていきます。
気づけば、最初は月1万円だった投資が、今では数百万円単位のリターンを生む存在になりました。
「投資って結局、やるかやらないか」
そして「続けるか、やめるか」だけなんだと、今は本当にそう思います。
7. 支出編:どう使わなかったか?
資産形成というと、「どう稼いだか」「どう投資したか」に注目が集まりがちですが、私にとって一番大きかったのは、“どう使わなかったか”、つまり「支出のコントロール」でした。
でも、ここで勘違いしてほしくないのは、
「ひたすら我慢して、何も買わずに耐えた」わけではないということです。
むしろ私は、コーヒーも飲むし、旅行にも行きます。
ただ、それを**「自分が心から欲しいものにだけ使う」**という基準に切り替えた結果、自然とお金が残るようになったのです。
■ 固定費を最初に最適化した
私がまず手をつけたのは、生活費の固定費でした。
これは毎月ほぼ変わらない支出なので、ここを見直すだけで貯蓄力が一気に上がります。
● 家賃
- 社会人1年目からずっと家賃10万円以下
- 昇給しても引っ越しせず、住居費を上げなかった
- 築年数より「駅近・安全・そこそこキレイ」を重視
● 通信費
- 格安SIM(楽天モバイル→LINEMO)に乗り換え
- 月額1,000〜2,000円程度
- 家のWi-Fiも安めのプランで十分
● 保険
- 生命保険・医療保険など一切加入せず
- 貯金があれば保険は不要という考え方(自己責任)
このあたりを見直しただけで、毎月3万円以上の節約になりました。
1年で約36万円、5年で180万円です。これが複利で大きな差になります。
■ 「浪費グセ」を分析して断捨離した
次に意識したのが、自分の浪費パターンの把握です。
例えば私の場合、もともとガジェットやファッションが好きで、ついつい新しいものを買ってしまうタイプでした。
でも、1年後に満足して使っていたものはごくわずか。
そこでこんなルールを設けました:
- 「それ、買った後に“語れる”か?」(自分にとっての価値を問う)
- 「1週間経っても欲しければ買う」(衝動買い防止)
- 「部屋にあるものを3つ手放してから新しく買う」
このルールが意外と効きました。
モノを買う基準が“満足度”や“納得感”になり、支出の質が上がったのです。
■ 節約を「ゲーム化」した
節約って、やらされるとしんどい。でも、自分で仕組みにしてしまうと楽しくなります。
私は支出を減らすために、いろんな節約術を**“ゲーム感覚”で試してみる期間**を設けました。
例えば:
- ふるさと納税で米・トイレットペーパーを大量確保
- クレジットカードを楽天経済圏に集中させてポイントを最大化
- 楽天証券×楽天カードで月5万円の積立 → 1%還元で年間6,000円ゲット
- PayPay・d払い・LINE Payなどキャッシュレスキャンペーンを活用
- メルカリで「今すぐ売れるもの」を5点探して即出品
こういった“遊び”が意外と効果的で、ストレスなく支出を減らす体質になっていきました。
■ 「贅沢をしない」ではなく「意味のある贅沢をする」
私は節約家ではありますが、ケチではないと思っています。
例えば、誕生日には少し高めのレストランに行きますし、推しのアーティストのライブには迷わず課金します。
このように、**「心が動くことには迷わずお金を使う」**と決めているので、普段の支出を無理に削っている感覚はありません。
- 「毎日のスタバ」より「月1回の最高の一杯」
- 「惰性の飲み会」より「心から会いたい人とのごはん」
- 「なんとなくの買い物」より「半年リサーチした買い物」
そういう基準に切り替えると、満足度はそのままで支出だけが減るんです。
■ お金を使わない「仕組み」を先に作った
- 給料が入ったら、自動的に投資口座に20〜25万円を移す
- 手元には“使えるお金”だけを残す
- 財布もアプリも見ない日を作る
こうすることで、そもそも「お金を使わない環境」を先に整えることができました。
貯金は“努力”ではなく“仕組み”で作るものだと、心底感じました。
■ まとめ:満足度はそのまま、お金は残る
節約と聞くと「我慢」のイメージが強いかもしれませんが、私の場合は**「取捨選択」**の連続でした。
お金を使う場所を選び、満足度の低い支出をやめただけ。
それだけで、無理なく、気づいたら貯まっていたという感覚に近いです。
「何にお金を使い、何に使わないか?」
この問いに真剣に向き合ったことが、5,000万円を達成できた最大の要因だったのかもしれません。
8. よくある誤解とアドバイス
私が20代で資産5,000万円を築いたと言うと、周囲からよく言われるのが、「才能があったんでしょ?」「もともと給料が高かったんでしょ?」という言葉です。
でも正直、それは誤解です。
この章では、私が資産形成の過程で感じた「よくある誤解」と、それに対して伝えたい現実的なアドバイスをお伝えします。
❌ 誤解①:「高収入じゃないとお金は貯まらない」
たしかに、収入が多いほうが有利です。でも実際には、年収よりも「貯蓄率」のほうが重要だと痛感しています。
私の年収が400〜500万円台だった頃でも、年間100万円以上は貯めていました。それが5年続けば、500万円です。
一方で、年収1,000万円あっても、毎月80万円使っていたら何も残りません。
「稼ぎより、残し方」という視点がなければ、いくら稼いでも資産は増えないのです。
❌ 誤解②:「副業しないとお金は増えない」
副業ができればもちろんプラスですが、副業で疲弊して本業に支障をきたす人も多いのが現実です。
私は副業をほぼせず、本業での昇給・転職によって収入を上げる道を選びました。その代わり、手取りをいかに最大限活用するかに全力を注ぎました。
- 支出を固定
- 投資を自動化
- ライフスタイルをシンプルに
結果的に、無理なく、かつ着実に資産を増やすことができました。
❌ 誤解③:「投資は危ない、減るかもしれない」
はい、減ります。でもそれが普通です。
投資を始めたてのころ、株価が少し下がるだけで不安になっていました。でも、今では「下がったらむしろ買い増しチャンス」とすら思っています。
株式投資は、短期で見ればリスク資産。
でも、**長期で見れば“価値を保ち続ける資産”**です。特にインデックス投資は、世界経済の成長を信じることに近い。
「長期で」「積立で」「分散して」。この3つを守れば、投資はギャンブルではなく、未来へのパスポートになります。
❌ 誤解④:「FIREは一部の人の夢物語」
FIRE(経済的自立と早期リタイア)というと、「一部の天才か、極限まで節約する人しか無理」と思われがちですが、それも誤解です。
私自身、今すぐリタイアするつもりはありませんが、**「働かなくても生きていける状態」**があるだけで、心がとても自由になります。
- 嫌なことを断れる
- 心からやりたい仕事を選べる
- 家族や友人との時間を最優先にできる
FIREは、逃げるための手段ではなく、選択肢を増やすための手段です。
誰でも「小さなFIRE」から始められます。月5万円の配当収入でも、生活の自由度は一気に変わります。
❌ 誤解⑤:「我慢しないとお金は貯まらない」
ここも大きな誤解です。私は我慢より“選択”を重視しています。
- 安いから買う → 「本当に欲しいか?」で選ぶ
- 飲み会だから行く → 「会いたい人とだけ会う」
- なんとなくで支払う → 「これは私の人生に必要?」と考える
この思考の積み重ねが、自然と支出を下げ、満足度を上げてくれます。
つまり、「支出の精度」を上げれば、お金は勝手に貯まるのです。
✅ 読者へのアドバイス:今すぐできる3つのこと
ここまで読んでくださった方に、すぐ実践できるアドバイスを3つだけ贈ります。
1. 「収入-支出=貯蓄」ではなく「収入-貯蓄=支出」に切り替える
給料が入ったら、先に貯蓄と投資へ自動で振り分ける。
残りで生活すれば、自然とお金は残ります。仕組みが先、感情はあとです。
2. SNSの「キラキラ投資家アカウント」に振り回されない
X(旧Twitter)などには、資産を盛っているアカウントも多くあります。
焦る必要はありません。自分のペースが一番強いです。
3. 「お金を使う理由」を自分の言葉で持つ
お金は、単なる数字ではなく、人生をどう生きるかの選択肢です。
なんとなくの出費を減らし、「納得して使うお金」だけを残していきましょう。
✅ 最後に:誰にでも資産形成はできる
私は特別な才能があったわけでも、親の援助があったわけでもありません。
ただ、自分なりに**「何を大切にしたいか」**を考え、その軸に沿って行動しただけです。
「投資は怖い」「自分には無理」と思っていたあの頃の自分に、今ならこう伝えられます。
「心配しなくても大丈夫。始めてみれば、少しずつ変わるよ」
わたしが少しでもあなたの「資産形成の最初の一歩」になれたら嬉しいです。
9. 今後の目標と読者へのメッセージ
このブログもいよいよ最後の章となりました。
ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございます。
この章では、私自身がこれから目指していく「FIREの形」や、「これからどんな人生を歩みたいのか」についてお話しします。
そして最後に心からのメッセージをお届けさせてください。
■ 私が目指すFIREは「完全リタイア」ではない
まず前提として、私は「30代で仕事を辞めて、南の島でのんびり暮らしたい」と思っているわけではありません。
むしろ働くこと自体は嫌いじゃないし、自分が何かに貢献している感覚が好きです。
ただ、これからの人生においては、**“働かない自由”ではなく、“働き方を選べる自由”**を持っていたいと思っています。
- 「この仕事は意味がある」と思えることだけに時間を使いたい
- 自分や家族の体調が悪いときは、仕事を休む選択肢を持ちたい
- 誰かの顔色や社内政治ではなく、自分の価値観を軸に決断したい
そうした、**「人生のハンドルを自分で握る状態」**を目指して、これまで資産を積み上げてきました。
■ 次の目標:「小さなFIRE」から「選択FIRE」へ
現在は金融資産が5,000万円を超え、生活コストも低く抑えられているため、ある意味「セミFIRE」はもう実現しているとも言えます。
ただ、私の中で次に見据えているのは、以下の2つです:
1. 年間配当・資産運用益を「生活費」に近づける
- 高配当ETF(VYM, HDV, 配当貴族系)を追加して
- 税引後で年間120〜150万円ほどの配当収入を目指す
- 必要に応じて不動産投資も検討(ただし管理コストに注意)
2. 「働かなくてもいい」状態を基盤に、新しい挑戦へ
- 個人メディアの立ち上げ(ブログやYouTube)
- 資産形成支援やライフプラン相談などの副業
- 数年かけて「生活のための労働」から「自己実現のための労働」へ
■ 自由になるとは「何もかも手に入れること」じゃない
お金が貯まると、周囲の反応も変わってきます。
「うらやましい」「勝ち組だね」「楽そうだね」――そう言われることも増えました。
でも、正直に言うと、私は別に“勝った”とは思っていません。
ただ、少しだけ自由を手に入れたにすぎないのです。
- お金があるから悩まなくなる、わけじゃない
- 自由があるから幸せになれる、わけでもない
- 結局は「どう生きたいか」を自分で決められるかが大事
資産を積み上げたことで、自分の心に素直に、正直に生きやすくなった――それが一番の変化かもしれません。
■ 読者へのメッセージ:あなたにも、きっとできる
最後に、ここまで読んでくださったあなたに伝えたいことがあります。
もしあなたが今、
- 貯金がなかなか増えない
- 将来がなんとなく不安
- 投資を始めたいけど、勇気が出ない
- まわりと比べて焦ってしまう
そんな気持ちを抱えているとしたら、大丈夫。
私もまったく同じところから始めました。
最初は、月1万円の積立から。
最初は、家計簿のアプリをダウンロードするところから。
最初は、YouTubeで「NISAとは」って検索するところから。
どんな人でも、最初の一歩は地味で小さなものです。
でも、その小さな一歩が、1年後、3年後、5年後の人生を変える力を持っています。
資産形成は、才能でもセンスでもなく、習慣と仕組みの積み重ね。
あなたが「変わりたい」と思ったその瞬間が、すでにスタートラインです。



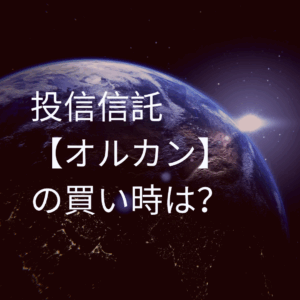

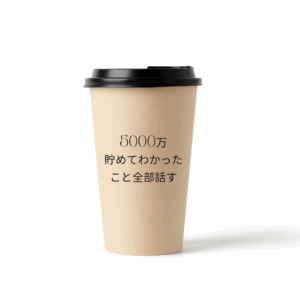

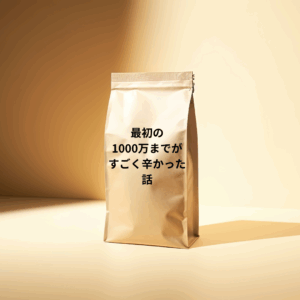

コメント